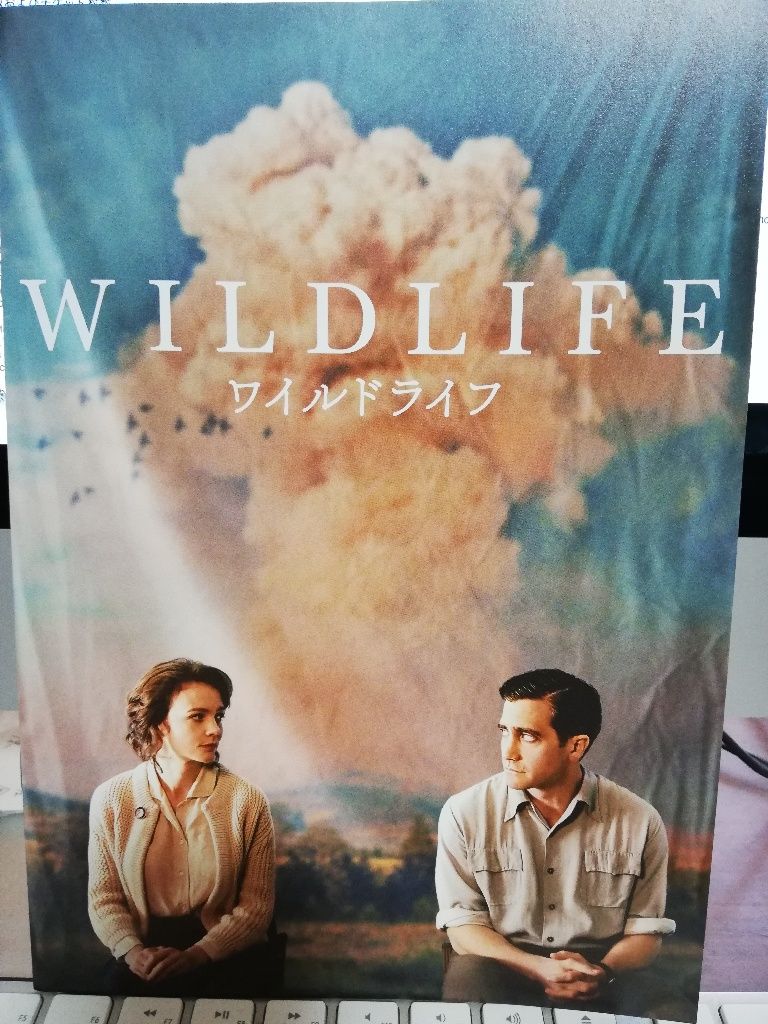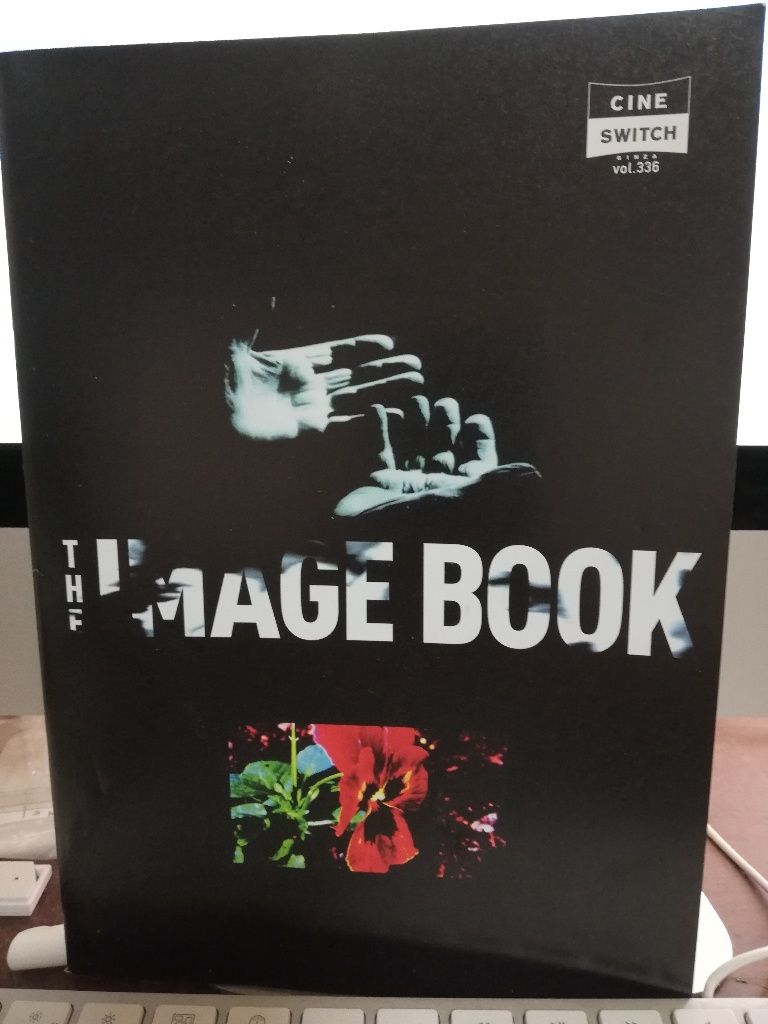しばらく前になりますが、アップリンク吉祥寺で映画「愛がなんだ」を観ました。
NHKの連続テレビ小説「まんぷく」で、主人公・福子(安藤サクラ)の妹役を演じ、一躍人気者になった岸井ゆきのさんの主演作です。どことなくだらしない男・マモル(成田凌)に一方的に恋をして、一方的に尽くすテルコを演じます。
「愛がなんだ」は、人気小説家・角田光代さんの小説のタイトル。この本が原作になっているわけですが、一方的に愛を尽くす主人公の物語なのに、なぜ「愛がなんだ」と愛を吐き捨てるようなタイトルなのでしょう。愛とは相手を思いやる気持ちで、相手が望まないことを押し付けようとはしないものです。無償の愛だからといって、タダだからと出血大サービスをして良いものではありません。しかしテルコは、「愛がなんだ」と、自分のやりたいように、相手が嫌がろうとも、平気で相手に尽くすのです。相手のための「愛」ではなく、自分がこうしたいという「欲」を優先するのです。
テルコのような女性はなかなかいないな、と思いましたが、よく考えると、世の中の「オカン」には、そういうタイプが結構いるような気がします。そうか、テルコはオカン体質なのか?
一方のマモルも、そんなテルコを振り切って、別の女性・すみれ(江口のりこ)に恋をします。彼女は相手に愛を求めず、自立した生き方を目指しています。だから、マモルにも愛を求めません。ゆえに、無理目の恋になってしまいます。
「献身的な愛」という言葉はあるけれど、「献身的な欲」という言葉はありません。そんなテルコの欲は、報われることはあるのでしょうか。それとも、欲から愛に、形を変える時は来るのでしょうか。